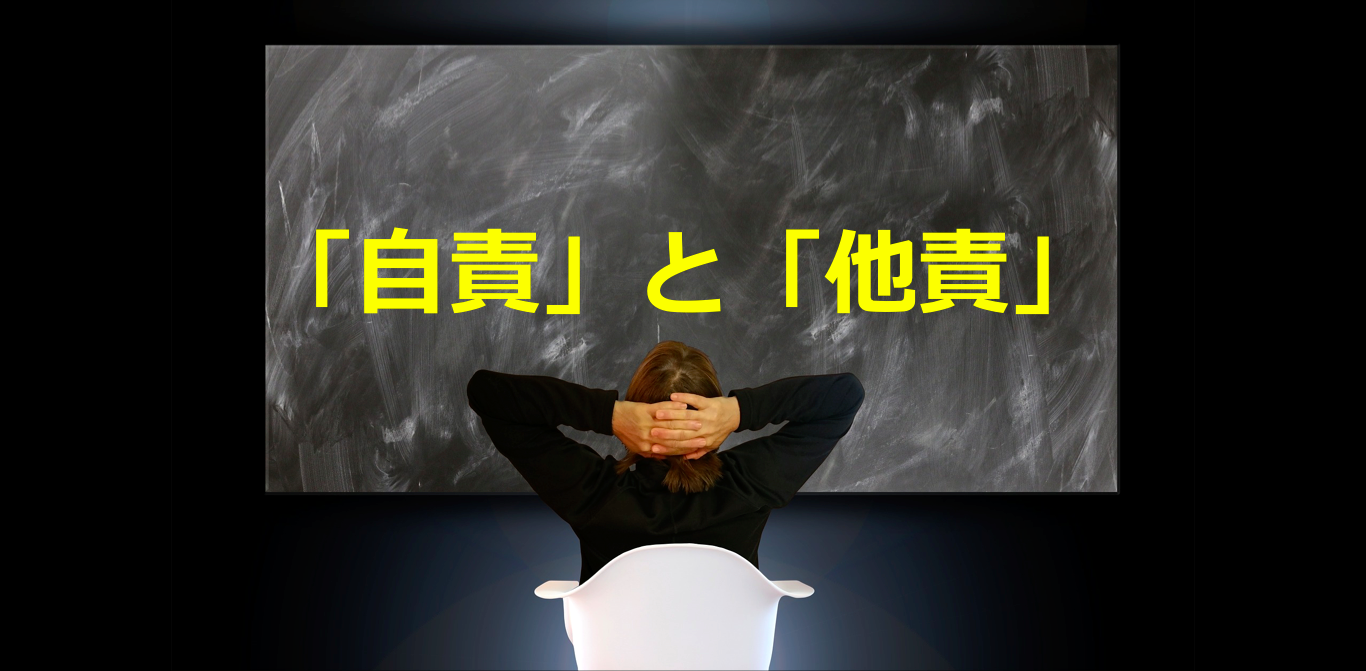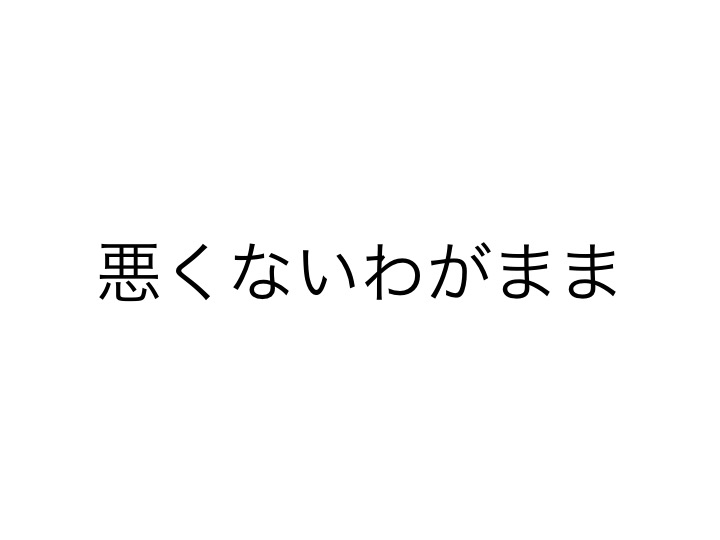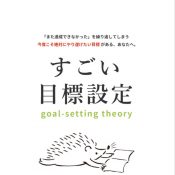親が果たすべき責任を役割から考える。子育てにおいて親が担うべき役割とはいったいなにか?

こんにちは。
すずきだいきです。
と考えると、いろんなことを経験させたいとか、危険な目には合わせたくないとか、食べるものには苦労させたくないとか、さまざまなことが頭に浮かびます。
このような質問は有益ですが、時として、どこかで大事なものを置き去りにしてしまう危険性があります。
一方で、
と考えると、私たちは簡潔にそれをまとめることが難しいように思います。
というのも、
臨床心理士で作家であるヘンリー・クラウドは、『「人を殺してはいけない」と子どもに教えるには―次世代に伝えたい10の“ルール”』という本の中で、親や次世代の育成にかかわる人には、主に次の3つの役割があると述べています。
- 保護者
- マネージャー
- スポンサー
「人を殺してはいけない」と子どもに教えるには―次世代に伝えたい10の“ルール”
ここでは、ヘンリー・クラウドが述べている親が果たすべき3つの役割を紹介します。
親として私たちに求められている役割とは、一体どのようなものなんでしょうか?
1、保護者
歩くこともできず、仕事をすることはもちろん、自分ひとりでは食事をすることさえできません。
多くの時間を眠って過ごしますが、起きているときにできるのは、ただ気分良く振る舞うか、泣くかといったことで、自分のいまの状態を必死に外界に発信することだけです。
ただ、自分には必要があり、どうにかしてそれを満たさなければならないということを知っているだけです。
子どもは、必要が満たされるものを親から受け取ることによって、自分に必要なものがなにか? なにによって満たされるのか? を学んでいきます。
歩くことができるようになったり、ある程度の自由がきくようになっても、なにが良いものでなにが悪いものなのかがわからない子どもは、目の前にあるものを気にせずに手に取り、口に入れます。
好奇心と柔軟な心と頭によって、さまざまな事柄を驚くべきスピードで吸収しますが、無知ゆえに目先の興味に捉われて危険に身をさらすこともあるでしょう。
子どもには経験がなく、自分の限界というものがわからないからです。
危険から身を守るために、親は適切な境界線を設定します。
- 子ども自身の中にある危険
- 外の世界にふりかかる危険
- まだ早すぎる自由
- 決して認められない行為、邪悪な行動や態度(例…殺人や薬物の使用)
- いつまでも親に依存し、大人になりたがらない傾向
ヘンリー・クラウド『「人を殺してはいけない」と子どもに教えるには―次世代に伝えたい10の“ルール”』p.17
2、マネージャー
子どもは、身勝手に自分の必要を主張し、それを押し通そうとすることがあります。
それは、どこまでが自分の権利で、どこまでが自分の責任か? 何をすると人が喜び、何をすると人が悲しむのか? が理解できていないからです。
その
この変化には大きな葛藤を伴いますが、その時に、親は子どもが
その領域は、家の片付けや、食事のマナー、挨拶から、経済の扱いや、自分の成長に対する取り組みなど多岐に渡ります。
親に甘えるのではなく、ただわがままに振る舞うのではなく、自分で責任をもって社会の中で生きていくことができるように支援するのです。
良くも悪くも、マネージャーとしての役割によって、子どもは親の影響を強く受けます。
- 親が何を大切にしているのか?
- 親の常識はどのようなものか?
- 親はどのようにして自分の行動に責任をとっているのか?
- 子どもに対してどのように責任をとらせるのか?
- 安全に対してどう考えているか?
- なにをどう管理するのか?
- 人に対してどう関わるのか?
- 責任を果たすとはどのようなことなのか?
- 責任を取らせるのは誰で、そのためにどう行動するのか?
3、スポンサー(供給者)
子どもはなにも持たずに産まれてきます。
誰が彼らを養うのでしょうか?
産まれてきた子どもは、親から与えられるものによって生活をします。
その点で、
そうでなければ、子どもは生きていくことはできません。
子どもの成長に自分自身が大きく関わっていることを知ることができるという意味で、「与えること」は大きな喜びとなります。
しかし、
親が無節操にものを与えると、子どもはそれがあたりまえなのだと思い込み、自己中心的で要求の多い人間になる。決して感謝をしない人間になってしまう。
逆に親の与えるものがあまりにも少なければ、子どもは希望を持たない人間になり、目標に向かって努力してその実りを手に入れようとしなくなる。
ヘンリー・クラウド『「人を殺してはいけない」と子どもに教えるには―次世代に伝えたい10の“ルール”』p.19
ただし、
人というのは、プレゼントをもらうと、プレゼントを与えてくれた相手ではなく、その物に対して喜び、与えてくれた相手のことを忘れてしまうこともあります。
ペットであれば、物を与え続け、死ぬまで自分が世話をすればいいでしょう。
しかし、子どもは自立していきます。
だからこそ、
逆に
まとめ
保護者、マネージャー、スポンサー。親の役割って複雑なんですね。
 だいき
だいき
ただ与えればいいわけでもなく、ただ守ればいいわけでもない、ただコントロールすればいいわけでもなければ、ただ自由にさせればいいわけでもない。
非常に難しいし悩ましいことですが、このような役割があるということを知って、親としても人間としても成長していきたいいなと思わされました。
子どもは機械のように思い通りにはなりません。
でも、だからこそ、その子自身がその子なりの魅力を持っているんだなとも思います。
その魅力を、最大限発揮できるように、親としての役割果たしていきたいと思います。
では、今日はここまで。この本もぜひチェックして見てください!
「人を殺してはいけない」と子どもに教えるには―次世代に伝えたい10の“ルール”
学んだことで生き方を変えよう!そして一歩を踏み出そう!
===最後まで読んでくれたあなたに===
ウェルビーイグ心理教育ナビゲーターのすずきだいきが、LINE@で人間関係やセルフコントロールについてのお得な情報を配信します。
また、読者の方のQ&Aにも答えます。
今すぐご登録を!!
他では出さないつぶやきを中心に、特別な案内などもお送りしますのでお楽しみに。