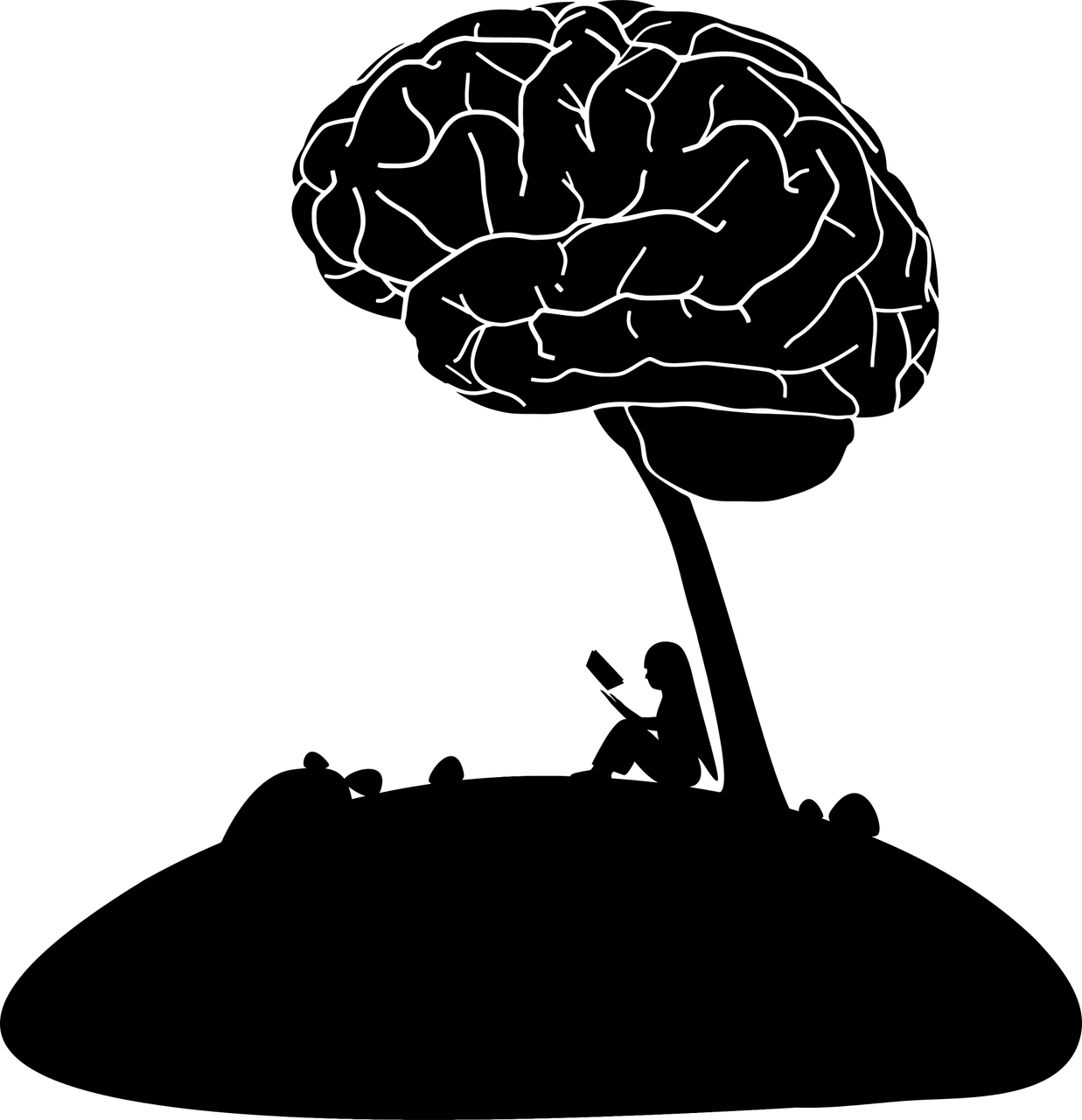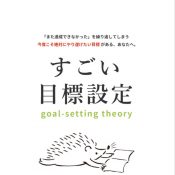速読は本で習得できるのか?できる理由とできない理由をあげてみる。
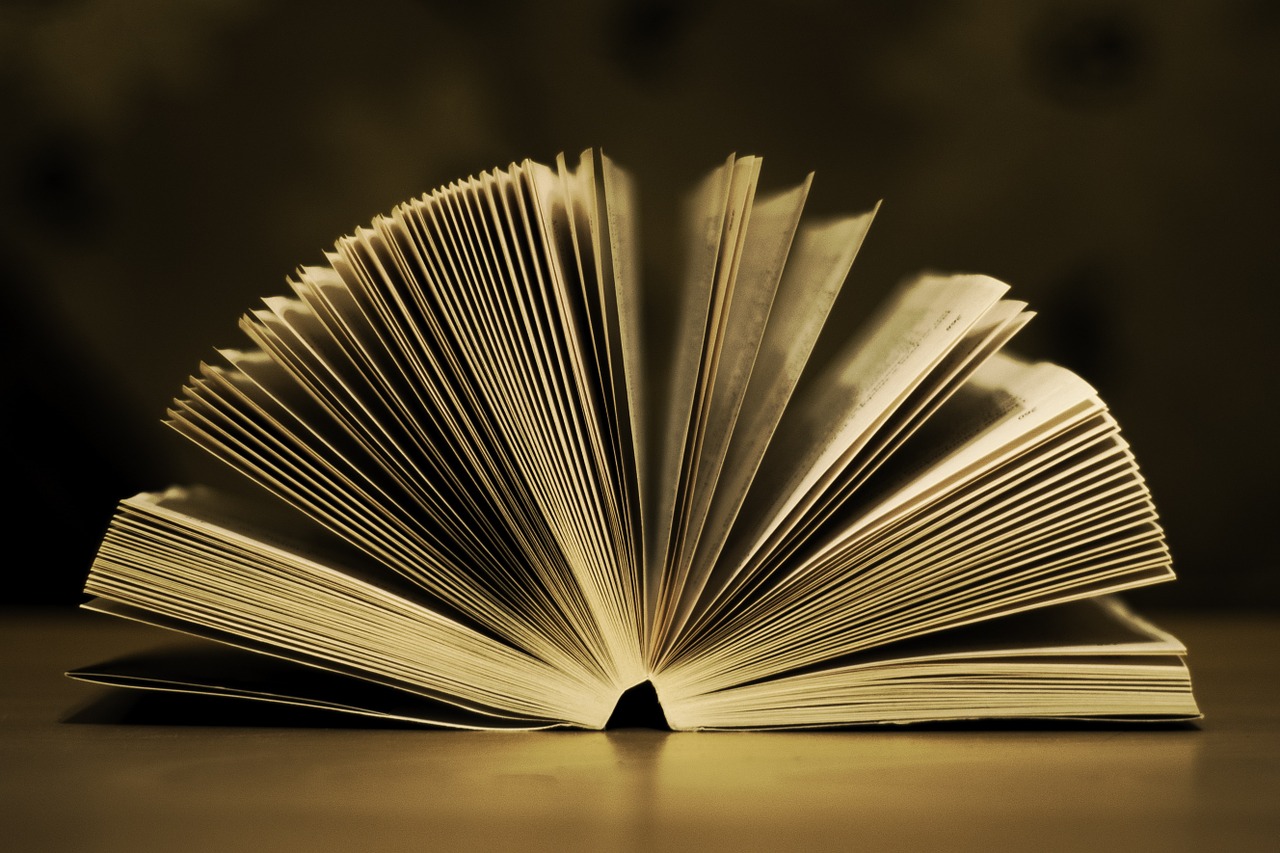
こんにちは。
速読インストラクターのすずきだいきです。
速読を習得したい人って、結構たくさんいるみたいですね。
速読教えてますって話しをすると、結構な人たちから、
「速読ね、できたらいいですよね。本なら読んだことあるんですけど、、、」
なんていうふうに声をかけられます。
で、それに続けて
「でも、本読むだけじゃできないんですよね。」
って言う人たちのなんと多いことか。
むしろ、そうじゃない人に出会ったことがありません。
速読を本で習得しようとして挫折する人って、ホント多いんですよね。
今日は「速読は、本で習得できるのか?」ってことについてお話しします。
結論から言えば、できないことはありません。
でも、モチベーションとセルフコントロール能力が極めて高い人じゃないと、本で速読を身につけるっていうのは難しいです。
まあ、プログラミングをやっている知り合いが誰もいない人が、独学で本を読んでプログラミングを習得するっていうくらいの難易度です。
だから、速読を本で習得しようと考えている人は、自分はそもそも結構ハードルの高いことにチャレンジしているんだってことを認識したほうがいいです。
速読って適切な訓練を正しいマインドで繰り返していくと、誰でもできるようになるんです。
にもかかわらず、それをあえて難しい方法でチャレンジして、速読そのものを諦めちゃったり、否定したりしてしまう人たちがいるのって非常にもったいないと思ってます。
なので、ここでは、
- 本で速読を習得するのはなぜ難しいのか?
- 速読習得のために必要なマインド
を説明しようと思います。
それでも、本で速読を習得したい人のために
- 速読を本で習得するために必要なこと
について解説していきます。
目次
速読は半信半疑からはじまる
速読って10年前、5年前より、目にしたり耳にしたりする機会が増えてきたように思いませんか?
ジャンプの裏に怪しく「速読!記憶術!!」って書いてあった時代は、今は昔。
最近では、ビジネス本ランキングでも速読関連の本がランクインしたり、勉強術や読書術系の本の中で速読が取り上げられるようにもなったりするようになってきました。
怪しい → オシャレ、カッコいい
へと時代が変わってきていることを感じます。
まあ、でも「1分間で5〜10ページのスピードで本が読めるんだよ。」って言われても、普通は信じられませんよね。
はじめて聞いた時には、「そんなもんがあるなんて信じ難い」って思うのが速読の世界です。
なので、多くの人は、
信じられない → 怪しい
っていうふうに結論付けてしまうんですよね。
人って
- 自分が見たこと
- 聞いたこと、読んだこと
- 経験したこと
の範囲でしか世界を見ることできないんです。
だから、自分の常識の外にある情報に触れると、
「そんな能力あったらいいんだけど、できるはずない。」
って思っちゃうんですよ。
ジャンプに脳みそのマークで「速読!記憶術!!」っていう広告が掲載されていた時代から速読はあったんです。
でも、怪しくてあまり受け入れられていなかったってところです。
最近は、ちょっとずつテレビに出てる学者とかコメンテーターとかが、「私、速読できます。」みたいに言ってたりするので、「本当なのかも!」「できたらいいな!!」って気にしてる人は増えてきています。
それでも、まだまだ眉唾物だと思われているスキルなので、ちょっと勇気のある人しか挑戦していないのが実情です。
本当に素晴らしいスキルなんですけどね。
速読を身につけようとする人はいつでも半信半疑がスタート地点なんです。
本を読んで速読に挑戦するということの難しさ
そんな時代の変化の中で、速読をやってみようという人たちが増えているわけですが、みなさん、とにかく手軽に触れてみようとまずは本を買ってみるわけです。
本を読む人と読まない人って二極化してる傾向を感じていますが、読む人はモチベーションが高くハングリーな人たちが多いので、速読にチャレンジしていく人たちも結構いるみたいです。
でも、本で言っていることをそのままやってみるって結構難しいんですよ。
たとえは、痩せるために筋トレしようと思って本を買って読んだり、動画を見たりしても、実際にそれを継続するのって難しいですよね。
同じなんです。
筋トレと速読って、共通点があるんですよ。
筋肉をつけるためには、継続して負荷をかけるトレーニングをしなければなりません。
同じように速読を習得するためには、脳の処理速度を速くしていくトレーニングが必要なんです。
でも、そのトレーニングはやればいいんだけど、継続することって結構難しいんですよね。
ましてや速読のスタート地点は、半信半疑であるわけです。
すると、どうなるか?
多くの人の失敗パターン
ここに多くの人たち通っていく速読の失敗パターンがあります。
- 半信半疑からのスタート
- 本を買う
- 実際に挑戦してみる
- 継続できない
- 速読を諦める
- 自分を正当化するために速読そのものを否定する
なんと悲しいことでしょうか、、、
一度は速読をしようと志すものの、最後には速読そのものを否定してしまう悲劇。
でも実際冗談にならないほど、こういうパターンをたどる人は本当に多いです。
本を使って速読を身につける成功ルート
速読を、本を使って習得するための成功ルートがこれです。
- 半信半疑からのスタート
- 本を買う
- 実際に書いてある通りにやってみる
- 読書速度を記録する
- 効果が感じられない時期を乗り越える
- 信じ続ける
- 諦めない
- なにかを掴む
- できるようになる
どうでしょうか。
実際、本を買ってその通りやってみても、右肩上がりに読書速度が上がっていくわけではない場合も多いです。
筋トレみたいに読書速度が上がらない停滞期もあります。
その時に必要なのは、
- 訓練を続けること
- 停滞期でも速読ができると信じること
- 書いてある通りにできているかを常に確認すること
- なんらかの工夫をしながら取り組むこと
です。
速読は誰でもできる
身につけたから言えるんですが、速読は誰でもできます。
本当です。
僕が言っているのは、飛ばし読みや斜め読みのことではありません。
脳の処理能力を鍛えて、ちゃんと一文字一文字読んでいるのに圧倒的な速さっていうタイプの速読ですかが、これ誰でもできますよ。
ごくたまにテレビで本を30秒くらいペラペラめくって、「はい、読めました」みたいな速読をしている人がいます。そういうF1スピードレベルの速読は、才能が必要だと思います。
でも、普通の厚さのビジネス本を20〜30分くらいで読み終わるっていうレベルの速読であれば誰でも習得できます。
そのために大切なのは、読み方のテクニックだけを身につけるのではなくって、脳を鍛えるトレーニングが適切になされている速読法を選ぶことが大切になります。
速読を分類してみる
速読っていくつも流派があるんです。
それによって、言っていること、やってること、トレーニング方法はかなり違います。
大きく分けると
- 潜在意識で読むタイプの速読
- 顕在意識で読むタイプの速読
- 飛ばし読み、斜め読みタイプの速読
です。
潜在意識タイプ速読代表:フォトリーディング
潜在意識で読むタイプの速読で、代表的なのはフォトリーディングですね。
- 写真を撮るように脳に本の中身のコピーを取っていく読書法
- 「フォトフォーカス」という、普段本を読む時には使わないような目の使い方をする
- それにより、普通短期記憶に入る読書での情報が長期記憶に保管される
- 「絵」としてインプットするので、記憶に残りやすく、アウトプットもしやすい
経営コンサルタントでベストセラー作家の神田昌典さんが中心となって、日本に紹介しています。
108,000円する2日間のフォトリーディング講座も、どんどん埋まるほどの人気なんだとか。
フォトリーディングの手順
- 準備(みかん集中法)
- 予習(文書をざっと見渡す、目的に沿った価値があるか検討する、読み進めるか否かを決定する
- 復習(文書の調査、トリガーワードの抽出、質問をつくる)
- 活性化(生産的休養、質問を見直す、スーパーリーディング、ディッピング、マインドマップを作る、高速リーディング)
なにを目的として本を読むのかで、入ってくる情報って全然違ってくるんですよね。
しっかりと記憶して知識としアウトプットできるような読書にするためのプロセスがしっかりと構築されているのが素晴らしいです。
ただ、僕にはフォトフォーカスの感覚が、本の説明だけではどうしても理解できませんでした。
何度もチャレンジはしているんですけどね。
できる人に話を聞いてみたいです。
顕在意識タイプ代表:川村式ジョイント速読術
「川村式ジョイント速読術」は、人間の脳の構造や仕組みを利用して、理論的に、効率よくトレーニングすることで、脳そのものを活性化させ、記憶力や速読力を身につけることができるようにしたものです。
- この速読法はアメリカと日本で特許を取得しており、現在、英語版速読術『eyeQ』はアメリカ国内のシェアナンバーワンとなっています。
- 引用:川村式ジョイント速読術HP
斜め読みや飛ばし読みではなく、実際に脳の処理速度を上げて、速く読むというタイプがこれです。
- 脳の構造や仕組みを利用したトレーニング
- 斜め読みや飛ばし読みではなく、脳の処理速度を上げで読書速度を高めていく
- 国内で唯一、特許取得の速読メソッド
- 英語版『eyeQ』はアメリカ国内のシェアナンバーワン
脳の処理速度を鍛えるプロセスが論理的に説明されているのが素晴らしいです。
たまに、本をたくさん読んだら速読できるようになったっていうセンス系の人が書いている速読本もあるんですが、それだと論理的な説明がなかったり、プロセスとして脳をちゃんと鍛えるっていうことをしないで、複数行を読み取れ!とか言われたりするんですよね。
でも、そういうのだと不器用なぼくにはわかりません。
その点、この速読法は、ちゃんと順を追って速読ができるように導いてくれるのでお勧めです。
飛ばし読み、斜め読みタイプ速読:レバレッジ・リーディング
本の16%理解できれば十分。極論を言えば、100項目すべてを抜き出して、一つも身につけないよりは、重要な一項目だけを抜き出して、それを実践するほうが、リターンを得られるのです。ささいな取りこぼしを気にしてスピードが遅くなるよりは、より少ない労力で大きなリターンを上げることに集中したほうがいいはずです。
引用:本田直之『レバレッジ・リーディング』
本の内容って別に全部記憶しなきゃいけないわけじゃないですし、必要な部分は一部ですよね。
- 本の中で重要な部分は一部分
- 目的をもって読むことで、その一部分をキャッチできるようにする
- 論文や資料作成の時に効果を発揮
- 読書で得たヒントをもとに、とにかく実践に生かす
以前、Read for Actionっていう、読書会に参加したことがあったのですが、「読書は実践に生かしてナンボ!」みたいなところがあって刺激的でした。
実践に活かしていく読書っていいですよね。
ただ、このマインドを持ちながら実際に速く読めるっていうスキルがあったら、もっといいんじゃないかというのがぼくの感想です。
飛ばし読みって、簡単なビジネス書とかならいいんですけど、難しい本には向いてないんですよね。。。
どの速読法が本での習得に向いているのか?
さてさて、速読法にも色々あるわけですが、ぼくのお勧めをお伝えします。
- 潜在意識で読むタイプの速読
- 顕在意識で読むタイプの速読
- 飛ばし読み、斜め読みタイプの速読
の中で、本で習得するならどれがいいか?
どれにもいい部分はあるんですが、ぼくのお勧めは
「顕在意識で読むタイプの速読」です。
というのも読書速度を数値化して測ることで、自分の成長を実感できるからです。
“フォトリーディング”って、フォトフォーカスっていう特殊な目の使い方をして、絵のように潜在意識に本の内容を取り込んでいくっていうんですけど、これがなかなかできないんです。
今まで”フォトリーディング”の講座に出た人たちには何人か会ってますが、「今では全然やってません」とか、「ゆっくり読むときにはすごく時間かかっちゃうんですけどね」っていう人もいました。
フォトフォーカスができればいいんですけど、それを本を読むだけで感覚をつかんでやるのは結構ハードル高いように感じます。
“飛ばし読み、斜め読みタイプ”の速読に関しては、その本からなにを受け取りたいかっていうことを明確にして、たくさん本を読めば、自然とできていくんじゃないかと。
自然にできるものに、わざわざ本で学ぶ手間をかける価値をあまり感じられません。
“顕在意識タイプの速読”は、トレーニングした分、脳の処理能力が速くなって効果が出てくるので、本で習得するのにも向いているといえますね。
速読を本で習得するのが難しい理由
さて、どの速読法が本での習得に向いているかをお話ししましたが、だからといってその道のりは甘くはありません。
本を買っても、それをもとにちゃんとトレーニングしていく必要があります。
最初にも言いましたが、買って読めば読書速度が速くなるわけじゃありませんから注意してくださいね。
本で速読の習得が難しいというのには理由があります。
なぜでしょうか?
最初は読書速度が上がっても体感しづらいから
読書速度が倍になったら、人ってどう感じると思いますか?
「今までと全然レベルの違う速さで読めてるぜ。イエーイ!!」
ってなると思いますか?
思いますよね?
少なくともぼくはそう思ってました。
でも、違うんですよ。
実は、読書速度って速くなっても、体感ではあんまり変わってるように思えないってことがあるんです。
ぼくもそうでした。
っていうのも、ちょっと脳の処理速度が上がって速く読めるようになった時って、すでに前の遅かった時の感覚、もう覚えてないんですよね。
それが一週間前のことだったとしてもです。
なんらかの方法で読書速度を計測してるならまだしも、速くなったか遅くなったかっていうのは、体感で知ろうっていうのはかなり難しいです。
ぼく自身の記憶を辿ると、ああ速くなったなあって感じたのは読書速度が分速3000文字を越えるくらいになってからでした。
分速3000文字って、普通の人から考えるとものすごいスピードですよ。
普通のなんもトレーニングしてない人ってだいたい分速600文字くらいですから、それと比べると5倍くらいのスピードであるわけです。
でも、ぼくが体感として速くなったなって思えたのは、そのくらいになってからだったんです。
まあ、感覚って極めて主観的なもんですからね。
それくらいを越えると、黙読してても頭の中では音読しているように文章をリフレインして読む状態から、視読といって見た文章を頭の中でリフレインせずに読みとれるようになっていきます。
視読ができるようになると、それまでの読書と違うことが自分でもわかってくるので、体感にもつながるといったところです。
逆を言うと、そのレベルまでいかないと、そういう感覚って得られないってことなんですよ。
人間、実際には効果があったとしても、体感できないと効果がないって主観で判断しちゃいます。
ここが、速読習得の難しいところですね。
実際に上がっている読書速度が、実際はそこまで体感できないことがある。
これが本での速読習得を妨げる一つ目のポイントです。
読書速度は落ちる?
で、ですね。
本を使ってトレーニングして読書速度が上がっても体感できないとみんなやめちゃうわけなんですよね。
諦めちゃうんです。
そうすると、それまでのトレーニングで上がってた読書速度も、落ちちゃうんですよ。
脳の処理速度を上げていくトレーニングすると、結構すぐに読書速度って上がるんですけど、それって実は短期的なもんなんですよね。
結局元どおりっていうんじゃ、ホント時間の無駄ですよね。
速読して時間短縮したかったはずなのに、逆効果です。
それでは、速読はトレーニングしている時しか速くならないのか?
というとそうではありません。
読書速度は定着するまでに時間がかかるということです。
だいたい、2〜3ヶ月同じ読書速度で読み続けられれば、そこから落ちることはあまりないといえるでしょう。
だからこそ継続が大切ってことですね。
近くに速読できる人がいないから
そして速読習得の挫折の理由No. 1がこれです。
- 近くに速読できる人がいないから
志高くひとりで速読をやりはじめても、本当に速読ができるっていう人がまわりにいないと続かないんですよね。
トレーニングを続ければ必ず効果は出るんですが、本でひとりでやってると、効果が出たり、実感したりする前に諦めちゃうんですよ。
「自分には向いてなかった」
「速読なんて嘘だ」
「続かないんだよね」
こういう内側から湧き出る声を打ち消さないと、本で速読は習得できません。
速読を本で習得したい人が選ぶべき本
どうすれば本で速読を習得できるのか?
長々と説明してきましたが、ここでどの本を選ぶべきかを発表します。
ズバリ、この本です。
これ読んでちゃんとやったら、読書速度はある程度は必ず上がります。
ということは、これでできないんだとしたら、あなたは本で速読を習得するということに向いてないということです。
なので、これで無理なら別の方法選んでください。
本で速読を身につける際の注意点
では、簡潔に速読を身につける際の注意点をお伝えします。
読書速度を記録する
自分の読書速度は必ず記録しましょう。
記録しないと、自分が速くなっていても実感が伴わずにモチベーションが下がる場合があります。
本の中に読書速度が確認できるページがありますので、そこは毎日欠かさすに。
速読ができると言っている人の情報に耳を傾ける。
速読は「できる!」と信じきることができるないかで、習得できるかできないかが決まります。
速読習得期間は、速読に前向きな意見をくれる人だけにそのことを話しましょう。
速読を否定しそうな友達がいたら、その人には速読のことを話すのはやめてください。
モチベーションが下がるだけです。
「速読なんてできない」
「どうせそんな速度で読んでも理解できない」
「一部の人だけの特別なスキルだ」
こんな声は百害あって一利なしです。
頑張れ
あとは頑張るだけです。
トレーニングができない日が続いても、気合いで再開してください。
いずれ効果が出る日がくるはずです。
まあ、本で速読を習得できる人はエリート中のエリートです。
自分がその中に入れると思うのであればぜひ、挑戦してみてください。
ぼくはあなたを応援します。
まとめ
さて、本で速読を習得できるのか?をお伝えしてきました。
原稿用紙20枚分お付き合いいただき、ありがとうございます。
速読は誰でもできます。
でも、本で習得するのにはいくつか超えなければならないハードルがあるので、それに負けずに頑張ってください。
ちなみに、これを読んでひとりでは速読はできそうにないなと思った人は、速読インストラクターのぼくに声かけてください。
本一冊分、2000円というの格安のお値段で、速読をスカイプでお伝えします。
時間も一時間なので、本を読むより速いです。
学んだことで生き方を変えよう。そして一歩を踏み出そう。
 原理から導き出した!速読術の3つのトレーニング方法
原理から導き出した!速読術の3つのトレーニング方法